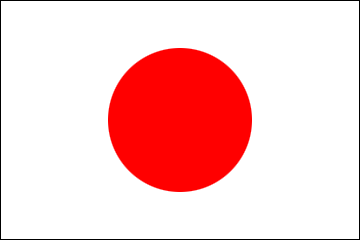根付とは?-「現代・木彫・根付展」を観に行く前に-
令和2年11月3日
こちらでは、根付の歴史や魅力についてご紹介しています。「現代・木彫・根付展」をより楽しんでいただくために、ご来場の前にぜひご覧ください。
根付の定義と特徴
渡邊正憲
根付は江戸時代に盛んに制作された小さな細工物です。和装文化華やかなりし頃、人々は印籠、煙草入れ、巾着などの提物を帯から紐で吊るして持ち歩きました。そして、紐の先端に取り付け、帯の下からくぐらせて帯の上部に固定させることにより、提物が落ちないようにする留め具としての機能をもたせたものが根付でした。当初は小さな瓢箪や象牙を輪切りにしたものなど、細工を施さない実用本位の素朴なものでしたが、次第に手の込んだ細密工芸品となり、様々な意匠を彫り込んだ美術的価値のある優れた根付が作られるようになりました。
根付が単なる小さな彫刻と異なるのは、留め具としての役割を果たす実用性にあります。そのためには、第一に紐を通すための二つの穴がなくてはなりません。そして、その穴に紐を通して帯に留めた時に、根付の意匠が正しい方向に向いている必要があります。動物が逆立ちをしたり、人物が背中を向けていたりするようでは、紐通しの穴の位置は正しくないということになります。現代は実用されることがほとんどなくなったため、申し訳程度に小さな穴を開けたものも見られますが、紐を通すことが出来なければ根付とはいえません。紐通しの穴は立っている人物なら背中、横たわる動物なら底部に開けるのが一般的ですが、人物の腕と胴体の間や動物の足と身体の間の自然な隙間を利用して紐通しにする方法もあります。
第二の条件は、根付を装着したり外したりする際に、着物や帯にひっかけて傷をつけるようなことがないように工夫することです。出っ張りが少なく、全体として丸みを帯びた形をしたものが機能的な根付です。
第三の条件は、四方八方どの角度から見ても手抜きなくきちんと彫られていることです。根付は置物のように置かれた状態で鑑賞するものではなく、掌に乗せてゆっくりと転がしながらすべての面を鑑賞するものです。それにより、思いがけない部分に作者の工夫や技巧を発見することも根付の魅力といえるでしょう。
根付の歴史
谷田有史
「根付」は巾着、印籠、たばこ入れなど、いわゆる「提げ物」を帯から提げるときに使う、いわば滑り止めの道具です。日本の着物には洋服のようなポケットがないことから、提げ物を持ち歩くには帯から吊るすしかありませんでした。
根付の語源としては、1.木の根を付けた、2.紐の根元に付けた、との二説があり、その起源については、いまひとつはっきりとしていません。江戸時代初期の風俗を描いた風俗画などを見ると、ブレスレットのような丸環形の根付で、提げ物を紐で結わえ、輪の部分に帯を通した様子が描かれたものがあります。このように提げ物を帯に止める用途に用いられたものは、古くから帯車、帯ぐる輪などと呼ばれています。ただ帯車は、いちいち帯を解かなければ提げ物を外せないので不便であったため、輪様のものは次第に廃れていきました。その後、当初は木の枝の輪切りや小さな瓢簞など身の回りにある天然のものが帯車に代わって使用されていたと想像されるが、それに彫刻や絵付けが施されるようになります。やがて仏師や面師あるいは木工・金工職人なども根付を手掛けるようになり、江戸時代中頃には根付を専門に作る根付師という職業も生まれました。
江戸時代中期以降に隆盛を極めた根付だが、明治維新(1868)を迎えて文明開化の世が訪れると、次第に和服からポケットのついた洋服へと服装が変化し、同時に新しい喫煙風俗として紙巻たばこ(シガレット)が登場したこと、発火具としてのマッチが登場することで大きな節目を迎えます。さらに、西洋文化を崇拝するあまり日本古来の文化は軽視され、明治以降、大量の美術品が海外に流出しましたが、根付も外国人によって収集される運命をたどります。根付の場合、この傾向は著しく、江戸時代に制作されたものだけではなく、明治時代・大正時代・昭和時代初期にわたって制作(輸出用として制作したものも含む)されたものも、その多くは海を渡りました。それは、太平洋戦争中の一時期を除いて戦後まで続きました。
根付の制作は、太平洋戦争後も細々と続けられていましたが、そうした状況の中、昭和46年(1971)にアメリカの根付コレクターであるロバート&ミリアム・キンゼイ夫妻が来日したことは、その後に活躍する日本人根付作家たちに大きなインパクトを与えました。キンゼイ夫妻は日本人根付作家たちに対し、江戸以来の伝統に依りかかることなく、現代的感覚で根付を制作するように強く勧めましたが、それに呼応した象牙彫刻出身の作家が独自の根付を創作しはじめ、「現代根付」の運動が起こりました。その中心となったのが、斎藤美洲、立原寛玉、桜井英之、駒田柳之らで、この運動が徐々に広がりをみせ、昭和52年(1977)には根付研究会が設立され、後には外国人作家も参加して国際根付彫刻会へと発展し現在に至っています。


「現代・木彫・根付展」概要ページはこちら