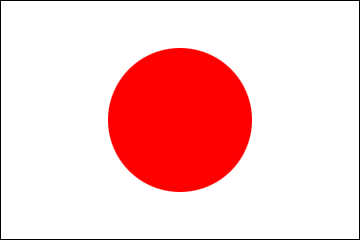井戸茶碗、国境を越えた信頼の絆と終わりのない努力
<記事原文>
https://www.gnnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=559591
日本で井戸茶碗と呼ばれる茶器の種類がある。井戸茶碗は、15~16世紀、韓国南部の民窯(庶民のために陶磁器を生産した窯)で生産された。生産当時の用途ははっきりとはしないが、独特な特徴があり、日本では茶道の精神と調和を成す茶碗として、大切に扱われてきた。
そのような井戸茶碗の再現に人生をかけた陶芸家が山清窯を営む閔泳麒(ミン・ヨンギ)先生である。閔泳麒先生は、1970年代に日本に渡り、人間国宝である12代中里無庵先生と13代中里太郎右衛門先生に5年間師事した。帰国後、山清窯を開き、陶芸活動を始めた。閔泳麒先生が井戸茶碗の再現に取り組む契機は、日本の陶磁器研究の大家、林屋晴三東京国立博物館陶芸室長(後に博物館次長)との出会いである。
400年前の陶磁器を再現するのは難しいことだ。陶磁器は土と釉薬の成分、陶磁器を焼く窯が決定的に重要であるが、これらに関する資料は伝わっていない。その上、当時の井戸茶碗は日本で大事に保管されており、接することも容易でない。だから、当時の井戸茶碗を知り尽くし、その本質を見極められない限り、再現はほぼ不可能だと言える。
林屋先生は、数限りない名品を鑑賞し、研究を重ねてきた見識家であり研究家である。素朴であるが風格があり、何度見ても飽きることのない独特の趣が井戸茶碗にはある。林屋先生は、韓国人の感性でなければ、当時の井戸茶碗を再現できないと考えた人物だった。
林屋先生と閔泳麒先生が井戸茶碗再現に取り組み始めたのは1990年。閔泳麒麟先生は、日に300個の茶碗をろくろで作り、その内10個だけを残し、残りは全て壊した。林屋先生は年に2回山清窯を訪れ、指導に当たった。閔先生も自作を手に年に数回日本を訪れ、指導を受けた。その際、林屋先生を通じて、井戸茶碗に直に接することができた。結局、閔先生が試作した井戸茶碗は30万個を超え、壊した茶碗はトラック1台分にもなった。
最良の師に出会えたことは大変な幸運だが、師の期待に背かないようにするためには途方もない苦痛も伴う。林屋先生から紙一枚ほどの微妙な重さ、厚さを指摘されれば、見かけは合わせられるようになったが、最大の難関は茶碗に「気」が入っていないと指摘されたことだったという。一体「気」とは何のことであり、どうすれば「気」を器に込めることができるのか、全く分からなかったという。
朝鮮時代の陶工達は、同じところに集まり、集団で生活した。年上の師が常にそばにおり、制作過程を見て子供たちは育つ。陶工達は知識がなかったが、自ずと事物を見る目は養われた。知識や欲があると純粋性が消え、純粋性が欠ければ人に感動は与えられない。「気」とは、まさに欲がない純粋な心のことだった。7年の歳月を経て、作風がかわり、風格を備えた閔泳麒先生の茶碗を手にした林屋先生は、「本当に朝鮮の井戸茶碗のようだ」と感嘆された。
林屋晴三先生は2017年4月永眠された。二人が目指したのは、当時の井戸茶碗のレプリカではなく、その本質を現代に再現する最高の作品である。閔泳麒先生の工房には数え切れないほどの釉薬と試作品が溢れ、閔泳麒先生は今日も最高の作品のため、汗をかいている。
韓国人の感性と日本人の眼識により、400年前の井戸茶碗の本質が再現された。閔泳麒先生の作品は、国境を越えた信頼の絆と終わりのない努力の結晶だ。閔泳麒先生は、日韓間の文化交流促進に貢献した功績により、本年8月8日、日本国の外務大臣表彰を受賞した。