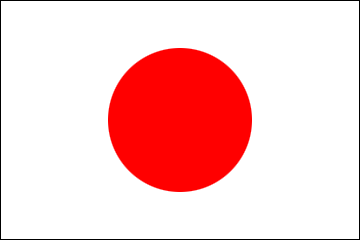韓国人の夫がいた日本人女性たちの涙ぐましい献身と奉仕
令和4年10月24日
http://www.civicnews.com/news/articleView.html?idxno=29642
國田房子さん、105歳にもかかわらず、女性医療及び生活保護支援を継続
田内千鶴子さん、「韓国孤児の母」木浦・共生園で3000名突破
釜山は開放性と受容性の高い都市、外国人を活用して発展が重なるよう
日本では9月第3月曜日が「敬老の日」。世界各地の日本大使館では敬老の日に合わせてその年100歳を迎える日本の高齢者へ表彰を行っているが、残念ながら韓国ではここ数年該当者がいなかった。さて、韓国に100歳を超える日本人がお一人いらっしゃる。今年105歳の國田房子さんだ。
1945年、國田さんは韓国人の夫、4人の子供たちと一緒に日本から釜山に来た。解放後の混乱、朝鮮戦争など当時の状況がどれほど過酷だったかは想像に難くない。唯一の楽しみは似たような境遇にいる日本人と話すことだった。後に日本人既婚女性の互助会である芙蓉会が設立され、國田氏が釜山本部会長になる。1965年、韓国と日本が国交を正常化し、國田氏は日本人既婚女性を一時帰郷させる事業を進めた。芙蓉会釜山支部は一時700人以上の会員がおり、多くの方々が國田氏の助けを借りて祖国に帰った。現在も最高齢者の國田さんは、高齢の日本人女性の医療支援や生活保護に役立っている。
韓国地域社会で活躍した日本人女性は國田さんだけではない。全羅南道木浦(チョルラナムド·モクポ)には田内千鶴子さんがいた。1928年、韓国人伝道師ユン·チホ氏は木浦で孤児たちと生活し始め、児童福祉施設「木浦共生園」を設立する。千鶴子さんは音楽指導を担当するボランティアだったが、ユン伝道師の活動を支援する中で、ユン伝道師の高い理想に感動し、一緒に韓国人孤児の世話を始める。2人は1938年に結婚し、苦労を重ねながら「共生園」を運営した。ところが、朝鮮戦争中に食糧を求めに出かけたユン伝道師が行方不明になってしまう。一人残された千鶴子さんは、かわらず孤児たちを木浦(モクポ)で育てた。千鶴子さんは1968年56歳で亡くなったが、その間共生園は3000人以上の孤児を育て社会に送り出した。千鶴子さんは「韓国孤児の母」として多くの市民から尊敬を受けた。
日本人女性といえば、先に述べた芙蓉会初代名誉会長の李芳子(イ·バンジャ)女史を欠かすことはできない。旧大韓帝国高宗皇帝の7番目の王子である英親王と結婚した李方子女史は、解放後、長い間韓国へ戻ることができなかった。1963年に韓国へ帰国した後は、韓国の障害者教育に力を入れた。知的障害児童施設である明輝院および知的障害特殊学校である慈恵学校を設立し、障害者教育の先駆者としてその確立と普及に努めた。
外国人が他国に住みながら、その地に根を下ろし、地域社会に貢献することは大変の一言で済ますことはできない程の困難が伴う。本人の強い意志とたゆまぬ努力が必要なのはもちろんのこと、さらに必要なのは外国人の活動を受け入れる地域社会の開放性と受容性だ。釜山という地域社会は多くの国内外の人々を受け入れながら活用し、発展を重ねてきた歴史を持つ。
釜山に勤めていた当時、釜山市の投資開発担当者から日本人学校を開発予定地域に移転することを提案されたことがある。外国人学校は地域開発の核心であり、外国人学校があることが大きな魅力になるという説明だった。この話を聞いた時、外国人学校を企業誘致と地域活性化の「資産」と考える釜山市担当幹部の洞察力に感嘆した。
「資産」になるのは学校だけではない。人も同じだ。現在、約6万4000人の外国系住民が釜山に住んでいる。彼らは韓国地域社会の構成員であり、釜山地域社会の一員として地域発展に寄与している。釜山が今後も開放性と受容性を維持し、国内外の多くの方々の心をとらえて発展を重ねていくことを願う。